今更聞けない?七草粥の種類と由来をご紹介!
※当サイトではアフィリエイト・アドセンス広告を利用しています。
すべて、通常価格1,250円(税込)のところkindle版(電子書籍)が
今だけの期間限定で20%OFFとなる1,000円(税込)で販売中です!
このチャンスを見逃さないでくださいね♪
さらに月額制サービスなら、すべて【無料】で読むことができるんです!
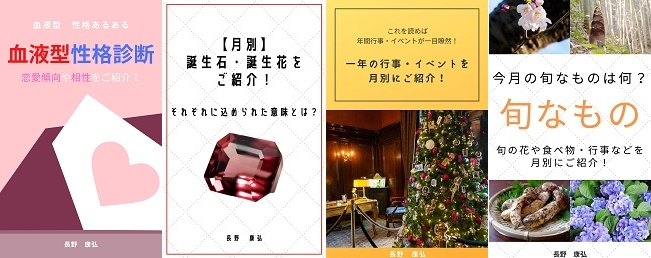

1月7日に食べる風習がある、日本の冬の風物詩の一つでもある”七草粥”。
今回は、そんな七草粥について詳しくご紹介させて頂きます。
「七草粥ってどんな種類の植物が入っているの?」
「そもそも七草粥を食べるようになった由来って何?」と言ったような、
今更人に聞くのは恥ずかしい七草粥の疑問についてお答え致します。
是非、七草粥の正しい知識を身に付けて、
日本の文化により親しみを持ってもらえると幸いです。
七草粥に入っている植物の種類は?

まずは、七草粥の中に入っている植物をご紹介致します。
”七草”という言葉の通り、種類は全部で7種類となります。
ちなみにですが、本来”七草”という言葉は「秋の七草」のことを指していたのだそうです。
今回こちらでご紹介する七草は、
七草粥の中に入っている”春の七草”をご紹介致しますので、
お間違えのないようお気をつけ下さい!
・セリ(芹)…セリ科の多年草。
別名シロネグサとも呼ばれています。
日本全国の山に自生しており、古くから食用として食べられている草でもあります。
「競り勝つ」という意味を持ちます。
・ナズナ(薺)…アブラナ科の草の一種。
別名ぺんぺん草とも呼ばれています。
田畑や道端など、日本各地で取ることが出来ます。
「撫でて汚れを除く」という意味を持ちます。
・ゴギョウ(御形)…キク科の草の一種。
別名ハハコグサとも呼ばれています。
かつては、草餅にも使われていた草でもあります。
「仏体」という意味を持ちます。
・ハコベラ(繁縷)…ナデシコ科の草の一種。
別名ハコベとも呼ばれています。
七草粥以外にも、おひたしや胡麻和えにして食べることが出来ます。
「反映がはびこる」という意味を持ちます。
・ホトケノザ(仏の座)…”コオニタビラコ”と呼ばれるキク科の草。
本来、ホトケノザと呼ばれているのはシソ科の草の一種となりますので注意。
「仏の安座」という意味を持ちます。
・スズナ(菘)…アブラナ科の越年草。
野菜のカブの葉の部分のことをスズナと呼びます。
カブの旬自体が冬となりますので、根も葉も美味しく頂けます。
「神を呼ぶ鈴」という意味を持ちます。
・スズシロ(蘿蔔)…アブラナ科ダイコン属の越年草。
野菜のダイコンの葉のことを指します。
ダイコンもカブと同様に冬が旬となりますので、
七草粥の時期に美味しく頂くことが出来るでしょう。
「汚れのない清白」という意味を持ちます。
上記の7つが”春の七草”と呼ばれている植物となります。
基本的にはこの7つの草を入れて七草粥は作られますが、
実は地域によって七草粥に入っている食材は異なります。
あなたの住んでいる地域ならではの七草粥を作って、美味しく頂きましょう!
七草粥はいつから始まった風習なのか?

続きまして、
1月7日に七草粥を食べる習慣がいつから日本で始まったものなのかを調べてみました。
そもそも七草粥は、
中国と日本のそれぞれ別の2つの風習が混ざり合って生まれた風習なのです。
まず、中国から”七種菜羹”という汁物の食べ物が平安時代の頃に日本に伝わり、
そして日本に元々あった”若菜摘み”という風習と混ざり合って、
七草粥の原型となる風習が生まれます。
そして、室町時代には汁物だった”七種菜羹”がお粥となり、
江戸時代には江戸幕府によって”人日の節句(1月7日)”が制定され、
この日に七草粥を食べるようになったことから徐々に民衆にもこの風習が広がり、
七草粥の風習は日本に定着していったと言われています。
ちなみに、”人日の節句”とは、五節句の一つであり、
1年に5回ある季節の節目のことを指します。
1月7日(人日)以外には、
3月3日(上巳)、5月5日(端午)、7月7日(七夕)、9月9日(重陽)が
五節句となります。
この人日の節句も元々は中国から伝わったものだと言われています。
七草粥の由来は何?
最後に、七草粥の由来となった”七種菜羹”と”若菜摘み”について詳しく調べてみました。
まず”七種菜羹”は、中国が唐の時代からあった風習で、
1月7日に7種類の草が入った汁物を食べて1年の無病息災を願うという意味が
込められていました。
ちなみに、昔の中国では新年にそれぞれの日を動物や人に見立てた占いが行われており、
1月1日は鶏、2日は犬、3日は猪、4日は羊、5日は牛、6日は馬、7日は人、8日は穀と、
それぞれ割り当てられていたそうです。
動物が割り当てられていた日はその動物を殺してはいけないとされており、
人が割り当てられていた1月7日は
犯罪者に対して刑罰を行わないようにしていたと言われています。
また、1月7日は中国では官吏の昇進を決める日でもありましたので、
”七種菜羹”を1月7日の朝に食べることで
立身出世を願うという意味も込められていたそうです。
続きまして”若菜摘み”は、古来の日本で行われていた風習のことです。
年の初めに芽が出始めた若菜を摘み取り、
この摘み取った若菜を無病息災を願って食べる、という風習なのです。
”七種菜羹”と”若菜摘み”はどちらも共通して
「無病息災を願って行われていた風習」だったのですね!
今更聞けない?七草粥の種類と由来をご紹介!のまとめ

今更人に聞けない七草粥の種類や由来などを中心に、
七草粥について詳しくご紹介させて頂きましたが、
意外と七草粥の歴史が古くて驚きましたね!
しかも、七草粥は日本独自の文化だと思っていたので、
由来が中国の風習だったことにも驚きました。
この記事を読むことで、
少しでもあなたの中にあった七草粥に対する疑問が解消されると嬉しいです。
改めて知ることが出来た七草粥の知識を元に、
七草の日は七草粥を存分に堪能することが出来ると良いですね!
.
すべて、通常価格1,250円(税込)のところkindle版(電子書籍)が
今だけの期間限定で20%OFFとなる1,000円(税込)で販売中です!
このチャンスを見逃さないでくださいね♪
さらに月額制サービスなら、すべて【無料】で読むことができるんです!
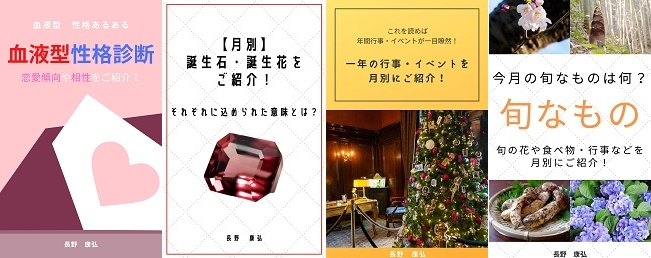

この記事を読まれた方は次にこの記事も読まれています








